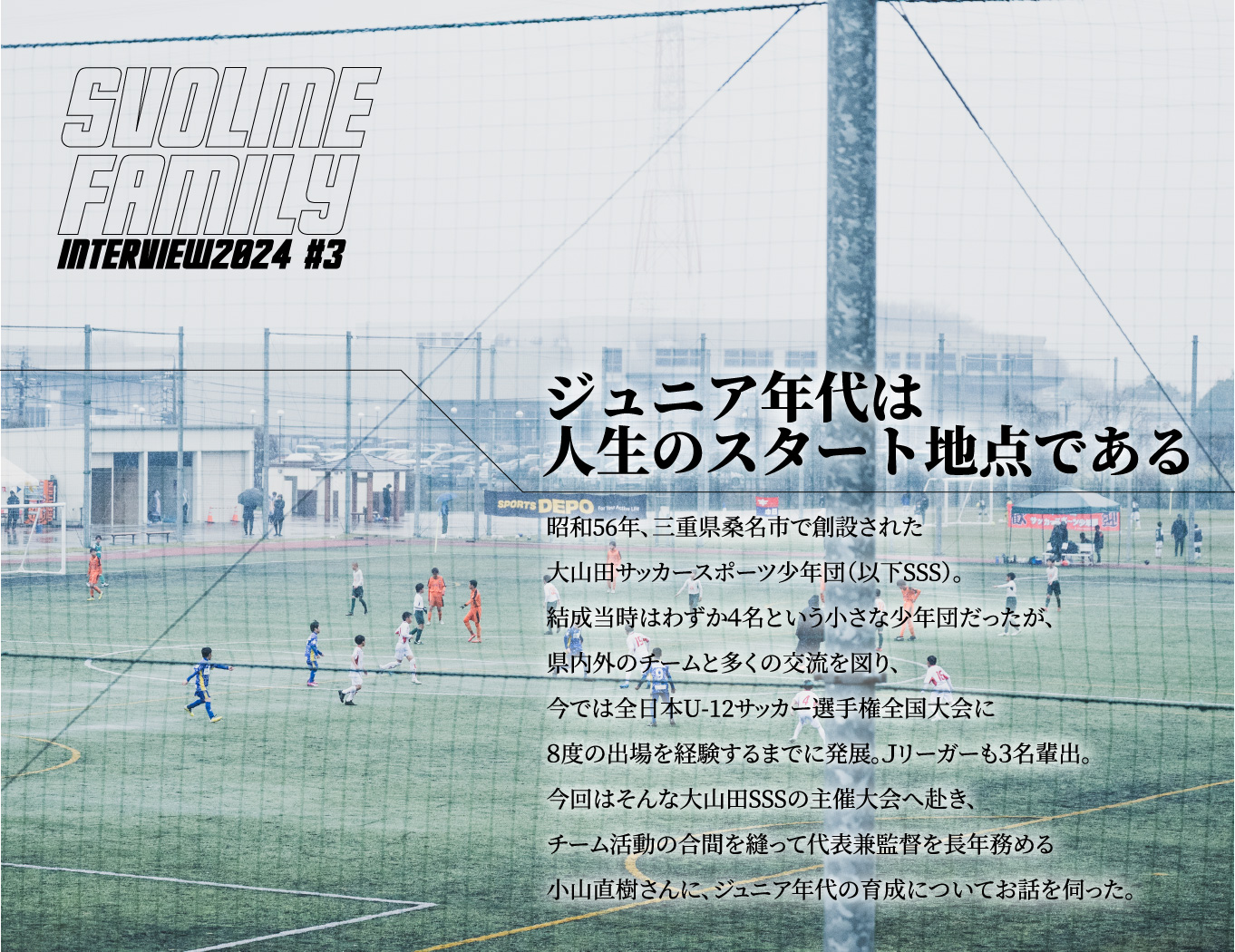



ーー大山田SSSが誕生してから今に至るまでをお聞かせください。
小山直樹代表(以下小山さん) 「挨拶のできる子供の育成と向上」をスローガンとして、1980年に設立し、私は6期生となります。設立当時はわずか4名の団員でスタートしたと聞いていて、三重県での初優勝は自分が選手時代1986年の新人戦でした。そこから徐々に大山田という名を三重で知らしながら、今では県内はもちろん、県外のチームとも多くの交流を図り、全日本U-12選手権大会では、8度の全国出場をするまでのチームとなりました。今も昔も変わらず、サッカーを通じて、集団の中で個人の社会性や責任感を養い、健全な心と身体の育成の一役を担うべく、スタッフ一丸となり日々、選手ファーストで真摯に向き合っています。
ーー小山さんがチームの指導でこだわっていることを教えてください。
小山さん 大きく分けると3つあります。1つ目は「選手たちの成長は全て環境(基準)で変わる」ため、基準を示して習慣化させること。2つ目は「自ら判断し考動(考えて動く)できる選手」となるよう、決めつけた伝え方をせず、答えを与えず、答えを引き出すように指導するということ。最後に3つ目は「ONもOFFも指導者は学び続けながら進化する」ため、インプットしたことをアウトプットして、基準を示すこと。ジュニア年代から原理原則を教えて、選手が主体性を持って取り組むことが必須であると思っています。ジュニア・ジュニアユース・ユース・大学や社会人(プロ)とある中で、ジュニア時代のインパクトがその後にどれだけ影響を与えるかは計り知れず、やはり一番大切な時期であると考えているので、大山田の活動を通して、選手たちをジュニアユースなどにしっかりと繋げられるようにというのは心掛けています。
ーー自ら判断して考動できる選手を育てるためには具体的にどんな働き掛けをしているのでしょうか?
小山さん 練習や試合中の声掛け、伝え方のところで答えを引き出すようなアプローチですね。例えば、ああしなさいこうしなさい、だとロボットになってしまうので、「今のプレーどうだった?」「そうだな、じゃあ他に何ができる?」「そうだよな、じゃあそういうのもやってみよう」など複数の選択肢を引き出すとか。低学年の子に対してはティーチング、高学年に対してはコーチング、と使い分けながらやっています。あと他の形としては、遠征に行った先でミーティングをした際に、3分間スピーチみたいなことを実践させ、今日の試合はどうだったか、良かったところ、悪かったところ、チームとしてどうしたい、ということを話す機会を作る。質問はその時々で変えるんですけど、そういうときにせめて3分間は、大人になってもしゃべれないといけないですからね、何かは話せた方が良いわけです。何々でした、ってすぐに終わっちゃっても、残り2分間、何でも良いから自分の力を使って表現してみる。そのような感じでコミュニケーションを図りながらやっていくということはしていますね。

ーー大山田SSSのチームとしてのコンセプトや特徴を教えていただけますか?
小山さん まず全体の目標に、”プロになるために何をすべきか考えて行動する”というものがあります。自主性、リーダーシップ、オフザピッチ、これらを軸に行動してほしいという話は常に選手にしていますね。コンセプトとしては、攻守にわたり連動した全員サッカー、堅守速攻スタイルを提唱しています。タフなゲーム展開の中でというのが大前提ですが、攻守の切り替え、攻撃的でボールを失わない、個性の発揮がポイントになってきます。メンタル面においては、育・感・力の3つを伝えていて、「育」は継続、向上心、「感」は一体感や責任感、感謝、感動、感じさせる表現力、「力」は協力、コミュニケーション力。プレーのところで試合の中で絶対に意識づけさせているのは、ゴールに向かう姿勢と、デュエルに勝つこと、ペナルティーエリア内の質の向上、テンポとインテンシティー(プレーの強度)を上げること。毎年末の全日に向けて、基本の質を追求していく。パスやコントロールの質、動きながらのテクニックなどのプレースピードや、球際の激しさ、アプローチの質、速さ、距離、予測などから、本気でボールを奪うということは高めていきたいですよね。
ーーJFAが掲げる2050年W杯優勝に向けて、ジュニア年代からどのような指導、取り組みが必要でしょうか?
小山さん これは技術に尽きると思います。ジュニア年代においてベースを作るというのは要するに技術なので。①止める、②蹴る、③運ぶ、④個を磨く、とありますが、こういう技術力の向上は絶対的に必要です。それに加えて、サッカー理解。サッカーIQとも言いますが、これもしっかりとできるようにしておくこと。あとはメンタルの部分ですよね。選手たちによく言うのは、”勝者のメンタリティー” と ”リバウンドメンタリティー”。負けず嫌いさを生ませるために、勝利至上主義ではないですけど、勝利のメンタリティーをもって、やるぞ、やれるぞ、いこうぜっていうところまで持っていく。また重要な試合とかで、先制をされて、そのまま下を向くのではなくて、よし切り替えてやろうぜって、リバウンドメンタリティーを持ち続けて、這い上がっていく気持ち。こういうメンタリティーを持っておけば、上にあがったときでもやっていけると思うんですよね。ベース作りの部分で補足をすると、僕らはSAQと言っていますけど、S(スピード)A(アジリティー)Q(クイックネス)。ラダートレーニングなどを取り入れて、小さくてもキュンキュンってかわすとか。大きな選手ばかりがプロになるわけじゃないので、大きくても小さくても、大きな選手はなおのことアジリティーが低い選手が多いので、俊敏性、機敏性のところにこだわりながらベース作りをしていくことは大事だと感じています。これはもう日本全体の意識がそうなっていけば良いなと思っていますね。
ーー大山田SSSは地元の選手を中心に構成している中で、直近5年で3回の全国大会出場、過去には全国3位に導いたという功績は輝かしいですが、実際に取り組まれていることを教えていただけますか?
小山さん 取り組みとしては、ピッチ上で体感させること、ですかね。口でああだこうだ言っても、選手って正直そんなに分からないと思うんですよ。例えば、スピードあるぞとか、テクニックあるぞとか言葉で伝えるよりも、実際に試合の中で敵と対峙させることで、目を慣らせば、どうやったら早い相手選手からボールを奪えるのかとか、そういうことを経験しているかどうかでは全く違うと思うんです。毎年、年度初めに大山田主催の大会を開いていて、そこで選手たちに基準を示して、その示した基準が習慣化しているかどうか、現状の立ち位置を確認するというのが恒例になっていますね。様々な特徴のある強度の高いチームと対戦をする機会を増やすために、関東・関西など、学びの旅(修行)にマイクロバスで出かけることも多々あります。その積み重ねが今の結果に繋がっているのかなと感じますね。この取り組みはこれからも変えずにやっていきたいですね。
ーー実際に対戦した相手の高いレベルを体感することで、自分たちの足りていないところや伸び代に気付くと。
小山さん 例えば、僕ら大山田は毎年小さな選手が多く、身体能力が高い選手は少ないので、組織的にサッカーをしようと言っているんですけど、8人制だったらマンツーマンで、相手のシステムに合わせてマッチアップでやったら、負けてしまうことが多いんですよね。個々の能力は相手の方が上回っているので。1on1で剥がされたらやられちゃうんだぞって。じゃあチャレンジ&カバーでボールを奪おうとか、立ち位置1つで変わるぞって。そういうのを実体験として感じてもらうことが大事だと思っています。

ーー小山さんご自身も親と指導者の立場で子育て、指導をされてこられた視点で、ジュニア年代の指導者、保護者で日々悩まれている方へ何かアドバイスやメッセージをお願いします。
小山さん そうですね、自分にも子供がいますし、三重県サッカーのアドバイザーもさせていただいており、よく話すこととしては、選手の自主性を持たせるために、自立させるために、試合などの準備は自分でやらせてほしいということですね。大山田の選手にも、低学年のうちから自分でやりなさいと。自分でやって何か忘れたら、もう忘れなくなるでしょうと。自信がなければ自分が準備した後に親にチェックしてもらうならまだいいと。他にも遠征や合宿に行ったときに、自分の住所と電話番号は言えるように書けるようにしなさいとか、当たり前だぞって。あと親御さんにいつもお話しすることは、親御さんってどうしても自分の子どもを中心に見てしまうところがあって、自分の子どもに対して、悪いことばかり言いがちなんですよね。試合やトレーニングを見て、あのプレーダメだったなとか、何やってんだとか。何か5つ親が言いたかったことがあるとしたら、まずは1つ2つ良かったプレーを見てあげてください、先に良かったことを言ってあげてくださいと。あの場面のプレーはしびれたよとか、あのゴールはすごかったとか。そうやって褒めてあげた後で、でもな、このときにこういうボールの失い方したけど、あれはこうやってキープしてほしかったなとか。そうすれば良かったことはそのままやろうとするし、ダメだったところも、手前で褒めてもらったことで聞き入れながら、ダメだったことも直そうと思えるので。褒められると素直に嬉しいから、褒められたことは継続するし、気になること、改善してほしいことも自然と取り組むようになってきます。僕なんかも厳しく言い過ぎちゃうときもたまにあるので、この部分はいつも気を付けながら、皆さんへのメッセージとしては、やはりしっかり褒めてあげてから、気になることを言ってくださいねと、お伝えできたらと思いますね。
=== 編集後記 ===
SVOLME FAMILY INTERVIEW 2024 #3-1 お読みいただき、ありがとうございます。
今回の取材対象は、三重県桑名市を拠点に活動するサッカー少年団、大山田SSSの小山直樹代表。
今年度で8回目の開催となる大山田CUPの大会2日目に、リーグ戦の合間を縫ってインタビューさせていただきました。
チームコンセプトや指導論についてお話し頂いた内容の中で、
小山さんが特に伝えたいワードの1つに「選手たちの成長は全て環境(基準)で変わる」がありました。
その”基準”をいかに高いところに持っておくか、
ジュニア年代の全国レベルを何度も体感している小山さんだからこそ軸にされていることなのだと思います。
それが大山田CUPをはじめ、三重県内外であらゆるチームと交流を図り、
肌感で経験させるという”基準”を示すということに繋がっているわけです。
また実際に感じたその”基準”を、今度は習慣化することで更なるレベルに引き上げていく。
選手たちの成長を、環境づくりと日々のトレーニング、2つの掛け算で加速させているというそのサイクルは、
本当に素晴らしいなと感じました。
今回のインタビューを通して、子どもたちの夢や目標を応援する保護者の皆さまには、
どの環境に身を置き、どんな基準を持てるかどうか、という視点を大切にしつつ、選手たちの成長を見守って頂けたら幸いです。
次週は大山田CUPに焦点を当てた記事をUPします。お楽しみに。





